去年と今年、十勝スピードウェイでロードスターパーティレースを観戦したのだが、ナンバー付きレースの出場スタイルがずいぶん変わったなと感じた。若いドライバーが増え、専属メカニックを帯同させ、アライメントゲージを持ち込み、タイヤは3セット以上持ち込み、さらにはマシンを積載車で運搬するチームもある。
私自身もFJ1600からレースを始め、似たような環境で戦ってきたが、ここまで本格的になっているとは思っていなかった。ナンバー付きレースでそこまでやるのか?と驚いたほどだ。こうした光景を初めて目にすると、これからレースを始めようとする気持ちが萎えてしまうのではないかと心配になるほどである。
この状況は決して好ましいことではない。だからこそ、この記事ではこれからナンバー付きレースに挑戦したいと考えている人へ向けて、前向きなエールを送りたいと思う。
目次(クリックでジャンプ)
結論|臆することなく挑戦してほしい

結論から言えば、最近のナンバー付きレースは確かに「ガチ化」が進んでいる。専属メカニックや大量のタイヤ、積載車まで持ち込むチームも見かけることがあり、初めて見る人にとっては敷居が高く映るのも事実だろう。しかし、だからといって臆する必要はない。すべてを完璧に揃えなくても、工夫次第で十分に戦えるし、結果を残すことも可能である。この記事では「やりすぎ感」に気圧されてしまいそうな人に向けて、レースの本質と始め方を改めて伝えたいと思う。
最近のナンバー付きレースがガチに見えてしまう理由
まずは最近のナンバー付きレースを見ていて驚いたことを紹介する。おそらく初めてナンバー付きレースを見た人も同じようにビックリするはずだ。
専属のメカニックが帯同
最初に驚いたのは、各ドライバーに専属のメカニックらしき人が1人はいることだ。しかもプロのメカニックの風貌をした人が多い。以前はお手伝いの人が1人2人ついている程度で、プロ級のメカニックを付けている人はほんの一握りだったはずだ。筆者が観戦したのが十勝スピードウェイでの一戦だったことも影響しているかもしれないが、それにしてもガチ感が強くて驚いた。
アライメントゲージ完備
次に驚いたのは、前日練習の最中にメカニックが急にアライメントを測りはじめたことだ。それも簡易的な計測ではなく、水平出しを行い、ダミーホイールを使って精密に測定しているクルマが4~5台はあった。パーティレースはセッティングを変えられる範囲が限られており、アライメントは数少ない変更可能な項目のひとつだ。それを手際よくピットで調整している時点で、メカニックがただの素人ではないのは間違いない。
タイヤとホイールを3セット以上持ち込み
さらに驚いたのはタイヤの持ち込み本数である。最低3セットは用意しているチームが多かった。異なる減り具合のタイヤを数セット用意し、コンディションに応じて選択しているのだ。しかもタイヤに合わせてホイールも種類を変える徹底ぶりである。新品タイヤでの出走が必須化される前のVITAで、筆者はユーズド1セットと新品1セットで戦っていただけに、その差に驚きを通り越して若干引いてしまった。
マシンを積載車で運搬
極めつけは、ナンバー付きレースであるにも関わらず、積載車でマシンを運ぶチームがちらほら見られたことだ。無駄に走行距離を伸ばさず、マシンの劣化を抑えるメリットは理解できる。しかし、ここまでくると「ナンバー付き」である必要性が薄れてしまう。ナンバー無しのレース並みの体制で挑む価値があるレースの証ともいえるかもしれないが、私は唖然とした。
ここまでしないと勝てないのか?|いや、そんなことはない(断言)
では、ここまでの準備をしないと勝てないのか? これからレース出場を目指す人はそこが一番気になるだろう。完全に私の私見にはなるが、「そんなことはない」と断言しておきたい。その理由を順に説明する。
半数は趣味のメカニック
実はプロっぽい風貌のメカニックの半数以上は、趣味で手伝っているメカニックだったりする。残りの半分はプロの自動車整備士、さらに残りがプロのレースメカニックといったところだ。厳密に数えたわけではないが感覚的にはこの割合である。ちなみにスーパーFJやVITAになると7割以上がプロのレースメカニックになる。パーティレースは今でも大人が趣味を楽しむ場として機能しているようだ。ただし、その趣味が突き抜けすぎてプロ顔負けになりつつあるのも事実だ。
アライメントを小まめに測る必要性は低い
アライメントは定期的に確認する必要はあるものの、サーキットでダミーホイールまで使って測定する必要はないと筆者は考えている。それでも現場で測定している場合は、走行中に異常を感じた、タイムが極端に出ないといった特別な理由があるはずだ。だとしても簡易的な計測で十分に対処できるので、無理してまでアライメントゲージを完備する必要性は薄い。
セッティングの選択肢は少ないほうが運転に集中できる
タイヤの選択肢が多いと安心感はあるが、逆に運転に集中しづらくなる場合も多い。特に前日練習と当日でタイヤを変えると、走り方を合わせ直す必要が生じる。その結果、セッティングは合っているのに運転を合わせ込めない状況も起こり得る。最初のうちはいかに運転に集中できる環境を整えられるかが重要である。タイヤは1セットでも問題は無いし、2セットあれば十分すぎる。
積載車は有効かもしれない…けど
積載車は車両の劣化を抑えるには有効な手段かもしれないが、その効果は限定的だと思う。おそらく積載車で運搬しているのは、マシンのパフォーマンス向上などよりも、積載車を元々所有しているチームが、機材をまとめて運べるなどの利便性を考えて使っているケースのほうが多いだろう。
石谷選手の例|腕と運があれば勝つことも可能
筆者は、上記4つをすべてやらずに優勝したドライバーを何人も知っている。その一例として、昨年のロードスターパーティレース十勝戦で優勝し、今年のレースでも3位表彰台を獲得した石谷選手を紹介したい。
彼とは筑波サーキットで知り合ったのだが、十勝戦に出場するとのことで応援に行った。彼はレース前日にフェリーで北海道に上陸し、ロードスターに積めるだけの荷物だけを持参して十勝スピードウェイに到着したのだ。準備したレース用タイヤも装着していた1セットのみ。工具はホームセンターで1980円ほどで売られているセット品。メカニックは学生時代の友人1人だけで、アライメントはフェリーに乗る前にショップで見てもらったようだった。
この日は他のチームのガチ感にも驚かされたが、彼の真逆のラフな体制にはもっと驚かされた。にもかかわらず、そのレースで彼は見事に優勝した。天候が大きく味方したことは間違いないが、それでも「自分ができる範囲で淡々と取り組んだ結果」掴んだ優勝だったといえる。

もちろん彼のドライバーとしての経歴は特別なものがあり、これからレースをはじめる人が真似するのは難しいとは思う。しかし、腕と少しの運があればナンバー付きのワンメイクレースで優勝することは可能だと証明してくれた。
まとめ|挑戦することで見えてくる世界
ナンバー付きレースの現場を見て「ここまで準備しないと戦えないのか」と感じてしまう人は多いかもしれない。しかし実際には、腕や工夫次第で十分に結果を出すこともできるし、楽しむこともできる。大切なのは、自分ができる範囲で挑戦を続けることだ。過剰な装備や体制に惑わされず、まずは一歩を踏み出してみてほしい。ナンバー付きレースは今もなお、誰でも楽しめる間口の広い舞台であることに変わりはない。挑戦した先にこそ、本当のモータースポーツの魅力が待っているはずだ。


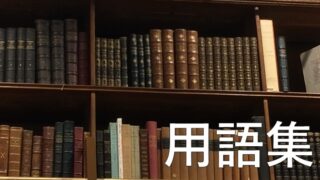




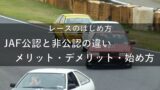



コメント