「N1」とは、JAF(日本自動車連盟)が定める市販車ベースのレース車両規定のひとつであり、ナンバー無しの競技専用車両によって争われるカテゴリーである。1990年代の耐久レース文化を支えた歴史的カテゴリーとして知られ、現在も地方選手権やクラブマンレースで広く採用されている。本記事では、N1の特徴、他カテゴリーとの違い、歴史、そして現代の運用までをわかりやすく解説する。
目次(クリックでジャンプ)
N1とは?
「N1」とは、JAFが定めるレース車両規定に基づき、市販車をベースに製作される“ナンバー無し・競技専用車両”によるカテゴリーである。大幅な改造が認められないため性能差が出にくく、ドライバーの技量とチームの総合力が試されるクラスとして長く親しまれてきた。
特に1990年代〜2000年代初頭に富士スピードウェイで開催された「N1耐久シリーズ」はN1カテゴリーを象徴する存在であり、のちの「スーパー耐久シリーズ(ST)」へ発展する原点ともなった。
現在でも、JAF規定としての「N1」は地方レースやワンメイクレースで活用され続けている。
N1の特徴
ナンバー無し・競技専用車両
N1車両は市販車をベースにしつつ、
- ナンバープレートの取り外し
- 内装撤去による軽量化
- ロールケージ・消火器追加など安全装備の装着
といった競技向けの仕様に変更される。
エンジン・足まわりの改造範囲は厳しく制限され、市販車に近い状態で走らせる点が特徴である。
日本の耐久レース文化を支えたカテゴリー
N1はスプリントではなく“耐久レース”を中心に発展したカテゴリーである。
富士スピードウェイでは10時間・24時間レースが行われ、
- ドライバー交代
- 燃費管理
- ピット戦略
など、チーム全体の総合力が試される場となった。
この文化が後のスーパー耐久(ST)につながっていく。
幅広い車種によるマルチメイク混走
N1は車種を限定しないため、GT-Rやランサーエボリューションのような高性能車から、シビックやヴィッツのようなコンパクトカーまで、多様なモデルが同じレースウィークで混走していた。
“身近な市販車がサーキットで全開走行する”という魅力が、観客人気を支えた大きな要因である。
- ▶関連記事:「マルチメイクレースとは?」
N1と他カテゴリーとの違い
Nゼロとの違い
- N1:ナンバー無し・競技専用車
- Nゼロ:ナンバー付き車両で参戦可能(公道走行可)
Nゼロの方が現行カテゴリーとして一般的で、初心者が参戦しやすい傾向がある。
- ▶関連記事:「Nゼロとは?」
NR-Aとの違い
- NR-A:ロードスター限定のワンメイク(ナンバー付き)
- N1:複数メーカーの車両が混走するマルチメイク
NR-Aはイコールコンディション重視、N1は車種特性を活かしたレース展開が魅力となる。
- ▶関連記事:「NR-Aとは?」
現在も存在するN1規定カテゴリー
かつての「N1耐久」はスーパー耐久へと発展したが、N1規定のレースクラスは今も全国各地で現「N1耐久」は名称としてはスーパー耐久へ発展したものの、N1規定そのものは今も現役である。全国のサーキットでN1クラスのスプリントレースが設定され、多くのアマチュアドライバーを受け入れている。
代表的な例は以下の通り。
- 富士チャンピオンレース(富士スピードウェイ)
FCR-86/BRZ、N1500/N1000、ロードスターN1など多彩なクラスを開催。 - もてぎチャンピオンカップ(モビリティリゾートもてぎ)
フィットをベースにした「もてぎFIT」がN1規定で実施。 - 岡山チャレンジカップ(岡山国際サーキット)
「N1-86」「N1ロードスター」などN1規定のクラスを継続開催。 - 北海道クラブマンカップ(十勝スピードウェイ)
「N1-1000」など小排気量クラスが根強い人気。
これらのシリーズでは、JAFが定めるN1規定の範囲で製作された競技専用車両が活躍しており、入門〜ベテランまで多くの層が参加している。
国内レースを一覧化した記事
N1の歴史と現在
N1は1990年代に大きな盛り上がりを見せ、富士スピードウェイの耐久シリーズが象徴的存在となった。公式シリーズとしての「N1耐久」はスーパー耐久として統合されたが、N1規定は現在もJAF競技規則に残り、地方レースの基礎カテゴリとして生き続けている。
つまり、N1は「歴史的カテゴリー」でありながら、今も“現場で息づく規定クラス”という二面性を持つカテゴリーである。
まとめ
N1とは、JAF規定に基づくナンバー無し・市販車ベースの競技専用車両で争うレースカテゴリーである。改造範囲が限られ、耐久からスプリントまで幅広く挑戦できるN1は、スーパー耐久の原点として歴史を築く一方、現在も全国のクラブマンレースで現役のカテゴリとして採用され続けている。
ドライバーの技術とチームの総合力が問われるカテゴリーとして、今なお多くの参加者にとって最良のステップアップの場となっている。


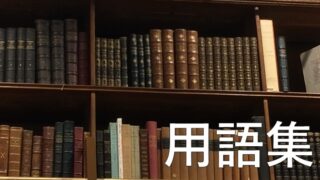

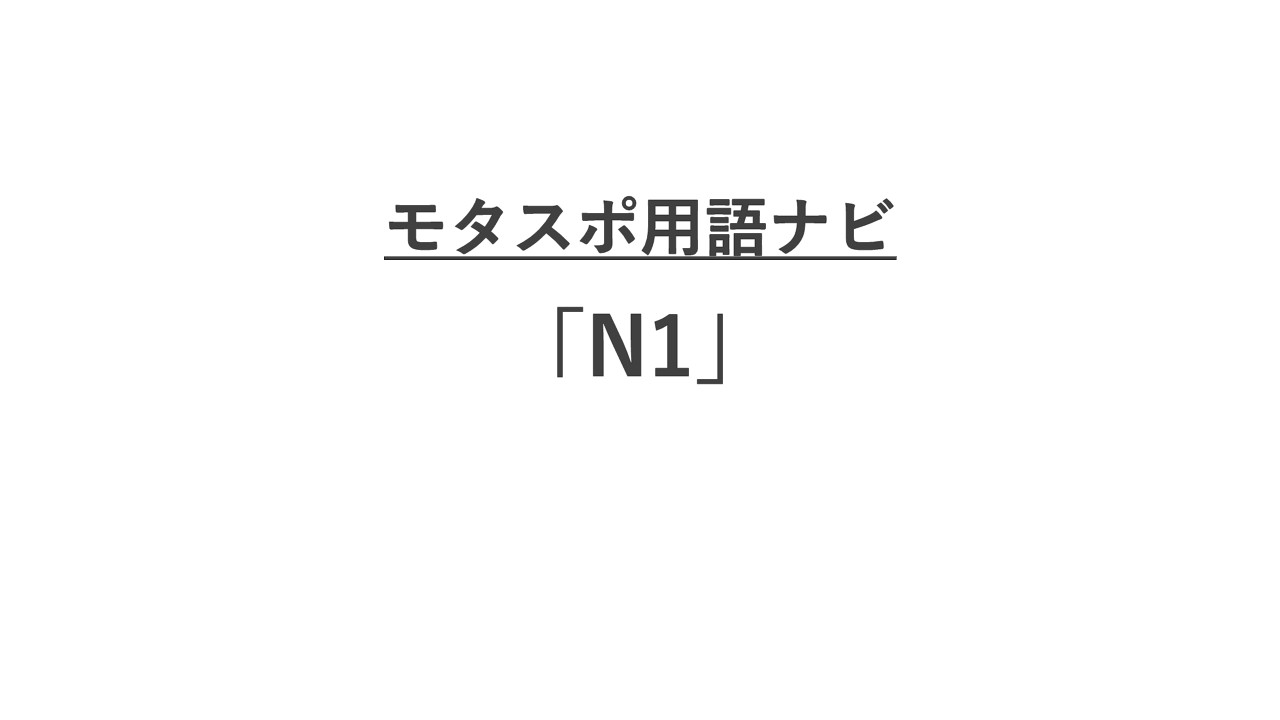




コメント